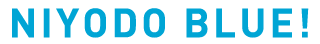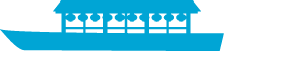五感で感じる仁淀ブルー!「仁淀ブルー体験博」

― もっと知りたい!仁淀川を楽しみたいあなたへ教える6つの体験 ―
圧倒的な透明度と青さで全国に「仁淀ブルー」という呼び名が知れ渡った奇跡の清流・仁淀川。
この仁淀川のある流域6市町村(土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)には、大いなる自然はもちろん、その自然のもとで昔から暮らす人々から生まれた様々な文化や歴史があります。
“その魅力を多くの人に知ってもらいたくて” と始まったのが、「仁淀ブルー体験博」。
2021年から始まり、毎年夏の終わりから秋にかけての期間限定で、6市町村それぞれから多種多様な体験プログラムが集まります。仁淀川に直接触れる川のアクティビティ、川の幸、山の幸を味わう食体験、人々の暮らす町を歩いたり、文化に触れたり、アートに挑戦したり。仁淀ブルーを味わえる、ここにしかない“とっておきの体験”をたくさんご用意しています。
夏から秋と実施期間は短いですが、実は期間中でなくても参加できる体験があるのはご存知ですか?今回はたくさんあるプログラムの中から、期間外でも受け入れ可能なものを6つ、今この文章を読んでくださっているあなただけにこっそり教えますね。
仁淀ブルーの真ん中で水上自転車体験!

仁淀ブルーの代表的なスポット“安居渓谷”と“中津渓谷”があるのが、最上流域に位置する仁淀川町。自然豊かな町内にはキャンプ場も多く、中でも”宮崎の河原キャンプ場”は、川の流れも穏やかで透明度も高く、多くの人で賑わう人気の場所です。そのキャンプ場に一番近い場所にあるアクティビティ施設が、仁淀川アウトドアセンター。川のアクティビティというベースで、毎年違った趣向を凝らし、体験博を大いに盛り上げてくれています。
舟底が見えるクリスタルカヤック、S U Pに水上こたつ。常時受け入れをしているアクティビティの種類も豊富ですが、今回お勧めしたいのは、水上自転車体験。一般的な自転車と同様に、足元に設置しているペダルを踏み漕ぐと、車体後方にあるスクリューが回って前に進みます。両側にしっかり浮きが付いているため、安定して水面を走ることができ、自転車に乗れる人なら誰でも挑戦できるという優れもの。車体もしっかり安定しているので、足元が濡れることはあってもほぼ確実に落ちません。体験はしてみたいけど、水に落ちるのは嫌といったアクティビティへのハードルも下げてくれるので、はじめての方に特におすすめです。
「水質が最も良好な河川」に過去何度も選ばれている仁淀川は、川底が見えるほどの透明度。川の流れに身を任せ、仁淀川の豊かな自然を満喫する時間は、ここでしか味わえません。
気軽に、手軽に仁淀ブルーを味わうには、まずここへ。
こちらの体験については、体験博以外の期間も公式サイトで受付中です。
(申込/問い合わせ:仁淀川アウトドアセンター https://www.niyodo.jp/ )

塩杜氏 銀象と作る"生"バスソルト体験

同じく毎年参加してくれているのが、土佐市の仁淀川河口に塩づくりの工房を持つ田野屋銀象さん。
海水を天日と風の力のみで自然乾燥させ、結晶化させる完全天日塩づくり。その製法を行う人は日本で見ても多くはなく、ここではさらに珍しい地下海水を使用。仁淀川が海と混ざり合う、河口という場所に工房があるため、黒潮の恵みだけでなく、仁淀川を流れる山の恵みも含まれた特別な塩ができあがります。
そんな田野屋銀象塩工房でのプログラムは、塩杜氏(しおとうじ)である銀象さん本人と塩小屋に入り、収穫作業を体験。普段生活で見慣れている“塩”ですが、収穫をしたことある人はほとんどいません。初めてつくりたての“塩”に触れると、あったかくてふわふわとした不思議な触感に、大人も子どもも「わっ」と歓声があがります。
過去4回の開催で特にリピーターが多いプログラムの一つ。だからこそいろんな声を聞き入れ、毎年内容の構成を見直しています。
2024年は、収穫体験と“生”バスソルトづくり。結晶化した塩の部分だけではなく、“にがり”の部分を入れ、半分液体、“生”な状態のバスソルトをその場でつくりました。
天然の保湿成分であるマグネシウムがたっぷり含まれた“にがり”の効果で、肌の保湿や老廃物を取り除くだけでなく、発汗作用も高く、体の中から疲れを癒してくれる優れもの。仁淀川の恵みを含んだ特別な塩の、さらに特別な“生”バスソルトを自宅に帰っても楽しめるスペシャルな体験でした。
こちらの体験については通常は受付していませんが、小グループでの工房見学は問い合わせ可能。直接問い合わせをお願いします。
(問い合わせ:塩杜氏 銀象 https://www.ginzo-salt.com/ )

体験博限定!酒蔵見学&鰻と司牡丹を楽しむ夜

慶長8年(1603年)創業の蔵元で県内に現存する最古の企業の一つが、佐川町にある”司牡丹酒造”。酒屋として長い歴史の中で、幕末の英雄・坂本龍馬とも縁深く「龍馬と最も縁の深い蔵元」としてもその名を知られています。
仁淀川水系の湧水の透明感を活かしながらつくられる淡麗辛口のお酒は、たくさんのファンに愛され飲まれ続けている逸品。また、司牡丹のある白壁造りの町並みは「酒蔵の道」と呼ばれ、かつては江戸時代土佐藩の筆頭家老深尾家の城下町でした。その佇まいは今もなお、佐川の町に歴史情緒を漂わせてくれています。
体験博では、そんな司牡丹酒造の貴重な酒蔵を特別に見学することができます。普段は入れない貯蔵蔵や、趣きのある「酒蔵の道」等を解説付きでご案内。そして、司牡丹が運営する”酒ギャラリーほてい”でお待ちかねの試飲タイム。司牡丹自慢のお酒を種類豊富に試飲させてくれる太っ腹ぶりに、お酒好きの参加者からは歓喜の声が飛び交います。その後は、地元で有名な老舗鰻料理専門店「大正軒」にて、鰻づくしの食事会。
美味しいお酒と美味しい日本酒のペアリングという特別な内容は、体験博のみの限定開催です。
酒蔵見学と試飲については、体験博以外の期間も相談可能(要予約)。城下町の風情漂う町並みを歩きながら、酒蔵見学に訪れてみてはいかがですか。
※普段受け入れ可能な酒蔵見学は、体験博での見学内容と異なります。
(酒蔵体験の詳細:https://niyodoblue.jp/experience/detail.php?id=44)

家でも作れる!特別な田舎寿司づくり

300年ほど前に、日下茂平という忍者が存在していたのは知っていますか?裕福な商家から米などを掠め取り、貧しい農民に分けていた“土佐の鼠小僧”と呼ばれる彼は日高村出身で、現在は“もへいくん”という村のキャラクターに姿を変えて愛され続けています。そんな日高村のプログラムの一つでは、忍者麻紗と名乗り活動している方が行う、一風変わった高知らしい体験ができます。
高知の街路市ではごく当たり前に売られている“田舎寿司”は、全国的にみても珍しい郷土料理。魚や昆布などが手に入りにくい時代、山で取れる食材でお寿司をつくったのが始まりで、高知の山間地域に伝わる行事食です。日高村でも昔から作られており、実際に田舎寿司の作り方が学べるプログラムとなっています。
日高村名産のトマトを入れた6種類の食材を切るところからスタート。切って、焼いて、味付けして、と説明を受けるだけでなく、自分で手を加えていきます。実は料理をするのが苦手、という忍者麻紗さんの最低限の手間かけレシピは、料理初心者でもハードルが低いというのが、このプログラムのいいところ。必要なのはやる気だけ。グループでも、家族でも気軽に楽しく参加することができます。炊き立てのごはんを酢飯に変えて、自分で作ったネタと握って、最後に盛り付けるところまで。出来上がった色とりどりのお寿司には、乙女心がくすぐられないわけがありません。帰る際には「ここだけの体験で終わらないように」と、実際に作ったネタと酢飯を持ち帰らせてくれるので、家でもすぐに再現が可能。こちらの体験については、体験博以外の期間も2名から予約可能。直接問い合わせをお願いします。
(申込/問い合わせ:貸切宿芽 https://www.yadoya-mysato.com/programcontents
案内人:忍者麻紗(河合)https://niyodoblue.jp/img_data/news-199_1.pdf?20250318165739)

山に囲まれ、旬を味わう!囲炉裏体験

いの町中心部から離れ、標高700mの山深い場所にあるのは、江戸時代中期に建てられた県内最古の茅葺き民家“山中家住宅”。高知県下で最も古く、特色ある山間民家として国の重要文化財に指定されています。現在、不定期ではありますが、この“山中家住宅”を使って、地域の食材を味わう囲炉裏体験が行われています。
普段味わうことのできない田舎体験ができるのが、このプログラムの大きな特徴。田舎といえばの “囲炉裏”に火をつけるため、薪を集めるところから体験は始まります。レクチャーを受けながら、上手く炎が燃えやすいように薪を組んで、いざ火起こし。薪が十分燃えてくるまでは、庭で竹串づくりに取り掛かります。茅葺き屋根の縁側に腰をかけ、まだ青々とした竹を削っていく作業には、普段の生活を忘れ、誰もがその一点だけに集中すること間違いなし。ふと手を休めると聞こえる山の音や、肌を掠める心地よい風に心が洗われていきます。あめご(あまご)に、豆腐に、じゃがいもを作りたての串に刺し、自分の田楽を持っていざ囲炉裏へ。パチパチと薪の音と立ち上がる煙とともに、少しずつ色が変わっていく様には思わず生唾がごくり。囲炉裏を囲んでの食事時間は、どこか昔の世界にタイムスリップしたのではと思うほど、風情があります。懐かしさを求めて県内外から参加をしてくれる年配の方から、昔の暮らしを全く知らない若い家族まで、幅広い方に楽しんでもらえる体験となっており、2024年の体験博では、囲炉裏体験とこの地域に伝わる本川神楽の特別なプログラムが催されました。
囲炉裏体験については、体験博以外の期間も季節に応じて内容が変わっていきますが、相談可能。直接問い合わせをお願いします。
(問い合わせ:synra(森羅)西田 TEL090-6281-0054 https://niyodoblue.jp/img_data/news-198_1.pdf?20250311130221)

土佐和紙を使って光に透ける和紙アートづくり

高知の山で育った楮(こうぞ)や三椏(みつまた)といった原料を、仁淀川の清らかな水で漉くと、土佐の山と川が育んだ強くて丈夫な和紙が完成します。日本三大和紙の一つである“土佐和紙”に魅了され、越知町で暮らす和紙アーティストの竹山美紀さん。和紙をもっと身近に感じてもらえるようにと、これまでの体験博でも様々なアートと組み合わせて提案してくれました。越知町の商店街にある”WASHI ORIORI”というお店で創作活動と作品販売、そしてワークショップを随時開催しており、過去に行ったプログラムも再体験することが可能です。中でも注目は、土佐和紙をちぎってつくる和紙アートづくり。
牧野博士の愛した代表的な植物である“バイカオウレン”をはじめ、文旦やカツオといった高知ならではのものから、動物、植物、モチーフなど。たくさんの下絵の中から、つくりたいものを選んだ後は、下絵に合わせて和紙を集め、貼りたい大きさになるようにちぎります。ただ”和紙”といっても、色だけでなく、繊維の残り具合や光の透け具合と、一枚一枚同じ紙はありません。どんな大きさで、どんな風に表現にするのかはその人次第。完成形を思い浮かべながら、ちぎって、貼って思い思いに表現していきます。細かい作業や難しい表現については、優しくレクチャーしてくれるので、難易度が高いものを選んでも大丈夫。完成した後も光に透けるとまた見え方が変わるので、さらに自分の作品を好きになります。美術に自信がない方でも気軽に挑戦できるのも、多くの人におすすめしたいポイント。観光と合わせて、持って帰ることができる体験もぜひ。
こちらの体験については、体験博以外の期間も2名から予約可能。直接問い合わせをお願いします。
(体験の紹介:https://niyodoblue.jp/experience/detail.php?id=68
問い合わせ: kuresora12@gmail.com “WASHI ORIORI” 竹山 )

最後に
今回は6市町村から一つずつ事業者さんをピックアップし、常時受け入れ可能な体験として取り上げさせてもらいました。
冒頭でもお伝えした通り、仁淀ブルー体験博は流域6市町村が一体となり、毎年夏の終わりから秋にかけての期間限定で、過去4回開催しています。(2025年3月現在)
事務局は仁淀ブルー観光協議会が務め、流域6市町村の観光担当者や事業者とともに“仁淀川”“仁淀ブルー”を軸にしながら様々なプログラム作りに取り組んでいます。ありがたいことに、参加者の中には毎年楽しみにしてくれているリピーターの方も。参画する事業者やプログラム数も増え、広がりが出ています。体験博期間だけの活動ではなく、年度初めには体験博に向けて全体で勉強会やプログラム作り、開催後には全体で反省会。と、参加事業者が皆、一丸となって取り組んでくれています。今回紹介した事業者さんのように、仁淀ブルー体験博で過去開催したプログラムから常時受け入れ可能なものに発展している体験や、そこからさらに発展を目指す事業者も多く、体験博が流域内の観光資源の掘り起こしやチャレンジのきっかけづくりにもなっていることを年々実感するようにもなりました。
年々パワーアップしている仁淀ブルー体験博。ここでの暮らしや文化を今後も多くの人に体験してもらい、次の世代に紡いでいきたいと考えています。
仁淀ブルーが好きで、この記事を最後まで読んでくれたそこのあなた。知らない仁淀ブルー情報はありましたか?今回紹介した体験や事業さんはもちろん、仁淀ブルーの楽しみ方はまだまだたくさんあります。仁淀ブルーとここで暮らす人々に会いに来て、もっともっとあなたの好きな“仁淀ブルー”を楽しみ尽くしてくださいね。
仁淀ブルー体験博公式サイト:https://niyodoblue.club/
これまでのプログラム開催動画:https://niyodoblue.club/menus/6681ff4a421aa900015c5b38
条件を指定して検索する